 仮想通貨
仮想通貨 【2021年】仮想通貨のエアドロップとは?今後行われるエアドロップや、受け取り方を解説!
暗号資産(仮想通貨)のエアドロップについて知りたい方向け。
この動画ではエアドロップの概要や受け取り方などを具体的に解説しています。
この動画を観ると暗号資産(仮想通貨)のエアドロップの仕組みや受け取り方が理解できます。
ブログ記...
 仮想通貨
仮想通貨 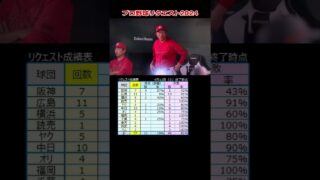 スポーツ
スポーツ  仮想通貨
仮想通貨  スポーツ
スポーツ  仮想通貨
仮想通貨 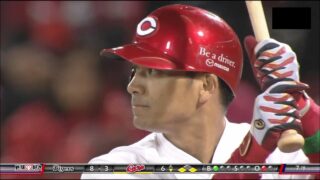 スポーツ
スポーツ  仮想通貨
仮想通貨 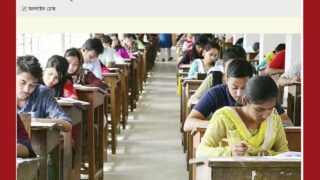 スポーツ
スポーツ  仮想通貨
仮想通貨  スポーツ
スポーツ